交通事故の示談交渉で、加害者側から提示された慰謝料が思ったより低く納得がいかないと感じてはいませんか?加害者(保険会社)から提示された示談の条件は必ずしも適正なものではありません。
したがって、交渉次第では慰謝料の増額が可能です。
交通事故に巻き込まれた被害者が、加害者から適切な慰謝料を受け取りたいという思う気持ちは当然のことです。この記事を参考にして慰謝料を増額させる方法をご理解いただき適切な慰謝料を受け取れるようにしましょう。
交通事故の慰謝料は増額できる
交通事故の慰謝料は、加害者側との交渉次第で増額させることが可能です。
しかし、被害者が一方的に慰謝料の増額を申し出たとしても、加害者側は受け入れてはくれません。なぜなら、示談を成立させるためには被害者と加害者双方の合意が必要だからです。
したがって、被害者は相手に納得してもらえる主張をする必要があります。そのためには法律と保険の知識が不可欠です。次の項目では、交通事故の慰謝料を増額させるために必要な「慰謝料」と「慰謝料基準」の知識についてご説明します。
交通事故の慰謝料とは
慰謝料の増額方法を知るには、まず交通事故における慰謝料の形態を知る必要があります。交通事故における慰謝料とは、事故に遭った被害者の「精神的損害」を補償するものです。
精神的損害とは、被害者が交通事故を被ったことで受けた「恐怖」や「悲しみ」といったものを指し、慰謝料をもって被害者の感じた精神的苦痛を補償します。
したがって、慰謝料は「治療費」や「車の修理費」といった財産的損害を補償するものではありません。
財産的損害についての詳しい解説は以下の記事を参照ください。
慰謝料の算定には3つの基準がある
慰謝料を算定する際には3つの基準が用いられます。3つの算定基準とは、「自賠責保険基準」「任意保険基準」「弁護士(裁判所)基準」です。
交通事故の被害者は、これらの基準をもとにして、加害者側に賠償請求を行うわけですから、3つの基準を確認することが重要です。
自賠責保険基準
「自賠責保険基準」とは、自賠責保険から損害賠償を受ける場合の算定基準です。自賠責保険とは、自動車損害賠償法によって、すべての車の所有者に加入が義務付けられている損害保険です。
自賠責保険は被害者の最低限の救済を目的に作られた保険ですから、補償額に限度がある点が特徴です。傷害事故については120万円、後遺障害を残した場合は3000万円(要介護の後遺障害は4000万)、死亡事故については3000万円が限度額となります。
したがって、自賠責保険によって賠償がなされても、被害者が納得できる充分な支払いが行われるわけではないという点に注意が必要となります。
任意保険基準
任意保険基準とは、保険会社が支払基準を算定する際に用いる独自の基準です。
保険会社の内部的な基準となるため、明確な算定基準が公表されているわけではありませんが、自賠責保険と弁護士基準の間に位置づけられていることが通常です。
任意保険基準は自賠責保険に比べて高額に設定されています。しかし、被害者が本来請求できる金額である弁護士基準と比較するとかなり低く設定されています。
したがって、任意保険基準で慰謝料を提示されたからといって受け入れてしまっては、被害者は損をする可能性があるため注意が必要です。
弁護士(裁判所)基準
弁護士基準とは、交通事故における過去の裁判例を用いて計算される算定基準です。弁護士基準は、法的な根拠をもった基準であり、裁判によって賠償金を請求する際にも用いられている正当な基準です。
弁護士基準は、自賠責保険基準や任意保険基準に比べ最も高額な慰謝料を請求することが可能です。したがって、適切な慰謝料を請求するためにも、被害者は弁護士基準を用いて示談交渉を行うと良いでしょう。
弁護士基準は被害者が直接加害者側と交渉する際に用いることも可能ですが、そのためには正当な根拠や証拠が必要であり、法律の知識に乏しい被害者が用いることは現実的ではありません。
被害者が弁護士基準で請求を行う際には、交通事故の案件に強い弁護士に示談交渉を依頼するのが一般的です。
交通事故で請求できる3つの慰謝料と相場
交通事故の被害者が請求できる慰謝料には3つの種類があります。
3つの種類とは、「入通院慰謝料」「後遺障害慰謝料」「死亡慰謝料」になります。それぞれの慰謝料の種類と相場を知ることは、慰謝料を増額させるためにも重要ですので、確認しましょう。
なお、それぞれの慰謝料の詳しい計算方法は以下の記事をご参照ください。
入通院慰謝料
入通院慰謝料とは、被害者が交通事故によって病院での治療が必要となり、それにともなって負わされた精神的苦痛に対して支払われる慰謝料です。怪我をして通院した場合に受け取る慰謝料ですから、傷害慰謝料とも呼ばれます。
入通院慰謝料は病院での治療日数と期間を参考に計算されます。したがって、治療期間が長いほど慰謝料が高額になるのが通常です。ただし入通院の実績がないと認められないため、負傷しても病院に行かない場合は支払いを受けられないため注意しましょう。
自賠責基準と弁護士基準を用いた入通院慰謝料の相場は以下のとおりです。
【条件】
- 症状:むち打ち
- 通院期間:6ヶ月(実質通院日数80日)
| 自賠責基準 | 弁護士基準 | |
|---|---|---|
| 入通院慰謝料 | 67万2000円 | 89万円 |
後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料とは、被害者が交通事故で後遺障害を負った場合に支払われる慰謝料です。
後遺障害を負った被害者は、一生その症状を負っていくことになり、多大な精神的苦痛を受けます。後遺障害慰謝料は、そのことについて正式に「後遺障害認定」を受けた場合に対して支払われる慰謝料です。
ただし、後遺障害もケースによって症状はさまざまです。したがって、後遺障害の等級によって慰謝料額は左右されます。
自賠責基準と弁護士基準を用いた等級別の後遺障害慰謝料の相場は以下のとおりです。
| 後遺障害等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
|---|---|---|
| 第1級 | 1100万円 | 2800万円 |
| 第2級 | 958万円 | 2370万円 |
| 第3級 | 829万円 | 1990万円 |
| 第4級 | 712万円 | 1670万円 |
| 第5級 | 599万円 | 1400万円 |
| 第6級 | 498万円 | 1180万円 |
| 第7級 | 409万円 | 1000万円 |
| 第8級 | 324万円 | 830万円 |
| 第9級 | 245万円 | 690万円 |
| 第10級 | 187万円 | 550万円 |
| 第11級 | 135万円 | 420万円 |
| 第12級 | 93万円 | 290万円 |
| 第13級 | 57万円 | 180万円 |
| 第14級 | 32万円 | 110万円 |
死亡慰謝料
死亡慰謝料とは、被害者が交通事故で死亡した場合に支払われる慰謝料です。
被害者に家族がおり、被害者の収入によって家族が生活していた場合は、被害者の死亡により多大な精神的苦痛を被ることになります。死亡慰謝料はそのような苦痛に対して支払われる慰謝料です。なお、死亡慰謝料の請求は被害者の遺族が行うことになります。
自賠責基準と弁護士基準をもとにした死亡慰謝料の相場は以下のとおりです。
| 被害者の立ち位置 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
|---|---|---|
| 一家の支柱 | 350万円 | 2800万円程度 |
| 配偶者など | 350万円 | 2500万円程度 |
| その他の者 | 350万円 | 2000万円〜2500万円程度 |
交通事故の慰謝料を増額させる5つの方法
これまでの流れを抑えて、交通事故の慰謝料を増額させる方法を解説します。
病院への通院実績をつくる
まず、入通院慰謝料を受け取るためには、「病院」へ通院した実績を残す必要があります。ここで指す病院とは、「整骨院」や「鍼灸院」といった治療院ではなく、医師が治療を行う「整形外科」などの病院を指します。
病院ではない治療院の場合、慰謝料の増額どころか本来請求できるはずの慰謝料すらもらえなくなる可能性があるため注意しましょう。
症状固定をするまで継続して治療する
入通院慰謝料を増額させるためには、「症状固定」までしっかりと治療を継続する必要があります。なぜなら、治療期間が短くなればなるほど、入通院慰謝料は減額されてしまうからです。
保険会社の多くは、被害者の治療が終わりそうなタイミングで「症状固定」の提案を出してきます。すでに怪我の治療が終了しているのであれば問題ないのですが、怪我が治っていない場合や違和感を感じる場合には、通院を辞めるべきではありません。
医師が症状固定をしたと認定するまで通院を続けることで、満額の入通院慰謝料を受け取ることができます。
交通事故の過失割合を交渉する
「過失割合」とは、交通事故を起こした原因が加害者と被害者のどちらにどの程度あるのかを示す割合です。
損害賠償請求では、過失割合をもとに請求金額が決定されるため、もちろん被害者側の過失が高くなってしまうだけ、受け取れる金額は減ってしまいます。保険会社の提示する被害者の過失割合は、被害者に高い割合で設定されている場合があります。
なぜなら、保険会社は営利企業であるため、利益を多く出すためには被害者に支払う賠償金を低く抑える必要があるためです。したがって、被害者としては過失割合の内訳を確実に把握し、自分の過失割合を少しでも低くすることで慰謝料を増額させることが可能です。
後遺障害認定は必ず行う
先述したように、「後遺障害認定」は慰謝料の算定に深く関係しているため、適切な等級認定を受けることが重要です。
交通事故に遭い、比較的重度の後遺障害を負っているにもかかわらず、自己判断で後遺障害認定を行わないまま示談を成立させてしまっては、本来受け取れるはずの慰謝料を被害者は請求できなくなります。なぜなら、示談は一度成立してしまうと後から内容を覆すことは原則として不可能だからです。
その上で誤った後遺障害等級の認定を受けてしまうと、被害者は不利益を被ることになります。後遺障害慰謝料に弁護士基準を用いた場合、等級が1つ異なるだけで慰謝料は200万円も前後してしまうためです。適切な慰謝料を請求するために、正確な後遺障害認定を受けるようにしましょう。
後遺障害の等級認定は保険会社の言いなりにならない
現在の後遺障害認定は、保険会社が深く関わる仕組みになっており、自分が納得のいかない後遺障害の等級を保険会社から提示される可能性があります。
簡単にですが、後遺障害認定を受けるまでの流れを説明します。等級認定を受けるためには、まずは医師の診察を受け、症状の記載された診断書を受け取る必要があります。
その上で、診断書をもとに保険会社や裁判所を通して審査が行われ、最終的な決定が下されるしくみになっています。
したがって、等級認定には保険会社が大きく関与する仕組みになっており、後遺障害認定において被害者が不利になる提案がなされる場合がまれにあります。
後遺障害等級の認定に納得がいかない場合には、保険会社へ「異議の申立て」を行うことができます。異議の申立を行い、正しい等級認定にしてもらうことは慰謝料の増額にもつながります。
保険会社の提案されるがままに手続きを行った結果、気づいたら納得のいかない慰謝料を受け入れてしまっていた、という例はかなり多いとされます。
後遺障害慰謝料を増額させ、納得のいく金額を受けとるためにも保険会社の提案をそのまま受け入れるのは避けましょう。
慰謝料を確実に増額させたい場合は弁護士へ相談を
慰謝料を確実に増額させたい場合は、やはり交通事故の案件に詳しい弁護士に依頼することが一番の近道といえます。なぜなら、弁護士に依頼することで「弁護士基準」の慰謝料を受け取ることができるからです。
先述したように、自賠責基準と弁護士基準では慰謝料の額に大きな差があります。弁護士基準こそが、本来交通事故の被害者が受け取るべきとされる賠償金です。
弁護士に依頼することで加害者側との交渉を全て弁護士に任せることが可能です。例えば、反省の態度が見られない加害者である場合も、弁護士を立てることで態度が変わる可能性もあります。
その上、保険会社との交渉においても弁護士に依頼することで交渉を有利に進めることができます。保険のプロである保険会社の担当者と、知識の乏しい被害者が直接交渉することは得策とは言えません。
交通事故に強い弁護士の場合、保険会社と対等に交渉を進めることが可能です。交通事故の慰謝料を増額させたい場合は弁護士への相談も視野に入れてください。
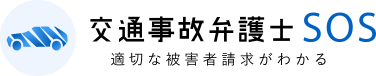


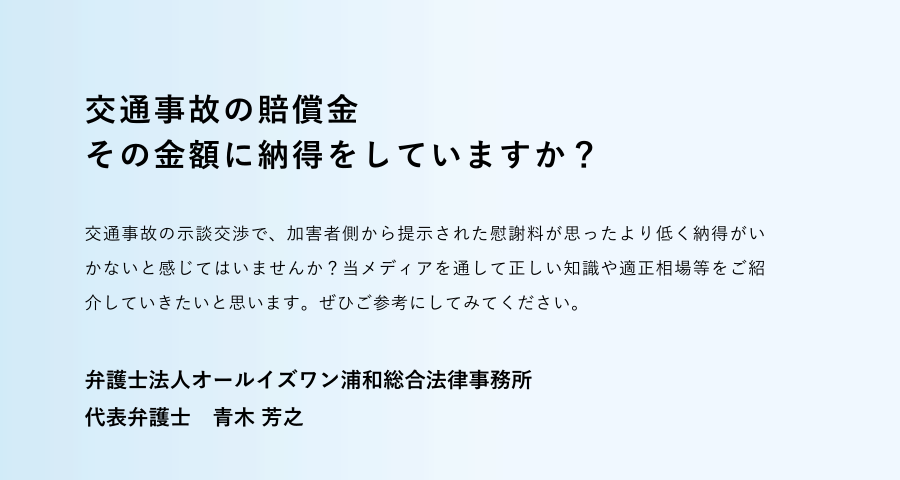
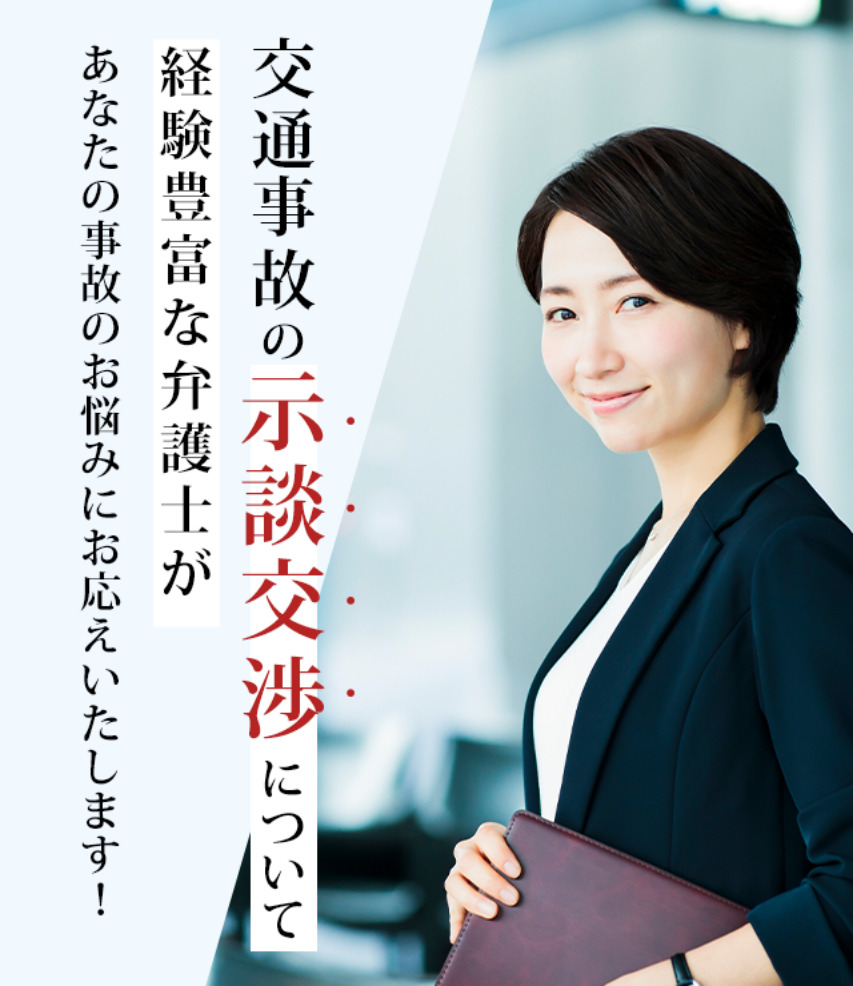
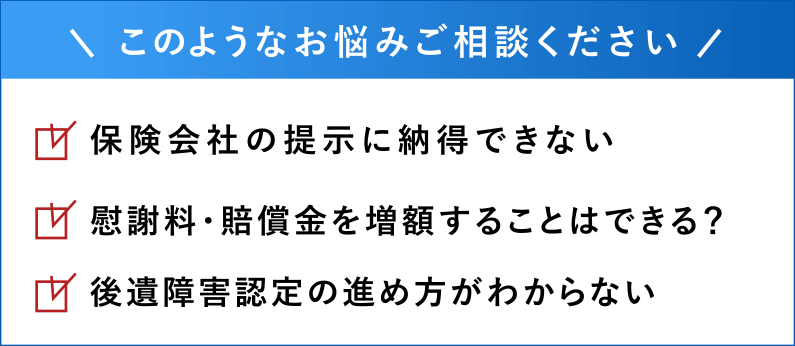
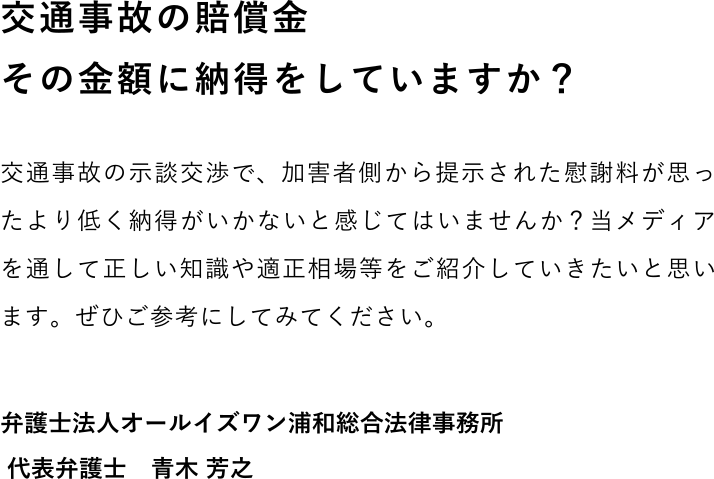



 電話で無料相談
電話で無料相談
 お問い合わせ
お問い合わせ